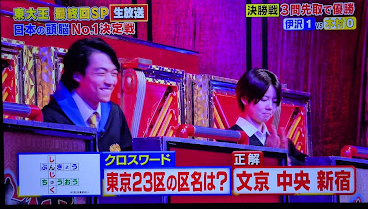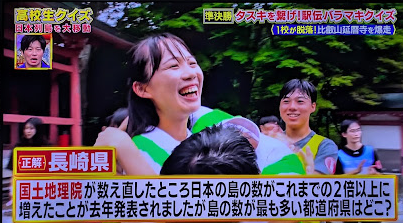top of page
284
総則編ⅩⅦ 答295~答314
314
答314 福島町吉岡です。そこに上陸した伊能忠敬一行は、1800年7月19日の「測量日記」に書かれている函館山での測量記録が蝦夷地での測量開始の通説でした。しかし「測量日記」の原本で忠敬の当時の測量記録「忠敬先生日記」には、それより前の7月10日の歩測の記録とみられる”陸地一里福島へ行”が書かれており、そのため福島町から測量が始まったとし、「伊能忠敬測量開始記念碑」が建てられたとのことです。
313
答313 「アナログ」でした。精密な地図を効率的に作るためには、①衛星写真より詳細に映る航空写真を撮影し、②航空写真から必要に家や道などを人間の目で抽出して描き、③それを基に樹木などで隠れているものが何であるかなどを現地調査で確認し、④地図に一つ一つ地図記号を記入し、⑤道路・河川などの情報を入れるなどのアナログ作業が重要であることが放映されていました。そのほか、昨年正月に起きた能登半島沖地震では、翌日には地殻変動が4m程あったことを発表するなど、国土地理院のほかの主な業務も紹介されていました。
312
答312 Bイースター島、Dニューヨーク、Cローマ、Aシドニー、F北極点、Eシンガポールの順でした。木村昴氏は全部正解し、賞金の1,000万円を獲得しました。
311
答311 「自然災害伝承碑」でした。全国で約2,000カ所記載されており、それぞれの碑がどのような災害で、どのような伝承がされているか記載されていました。なお地理院地図にも地図記号として表示されていることは、放映されませんでした。
310
答310 「1,500万個の台形の面積を計算する」でした。具体的な計算方法を、国土地理院地名情報課の塚﨑補佐が、屋久島を例に説明していました。地形の変換点をプロットして計算するとのことですが、簡単にするためプロットを地形の変換点をAからNまでの13点に簡素化し、その点からy軸に垂線を下ろして、AからGまでのそれぞれの台形の面積を計算し合算する。それだと海の面積が含まれるので、GからAまでの下側のそれぞれの台形の面積を引けば、屋久島の面積が求められる、とのことです。変換点の数が台形の数となり、実際には市区町村ごとに面積を出していることから、全国では1,500万個の台形の面積を計算しているとのことです。また埋め立てや地殻変動(最近の大きな変化として、小笠原の西ノ島新島を挙げていた)などがあるので、年に4回公表しているとのことでした。

309
答309 標高3776mの富士山頂の方が、犬吠埼より4分早く日の出が見られるとのことです。
308
答308 東武アーバンパークライン、北総線及び新京成線が交差する新鎌ヶ谷駅前に表示されていました。表示線の先には、鎌ヶ谷市による”世界につながる東経140度線”とのタイトルで、説明版があり、その向こうにも東経140度線が引かれていました。
307
答307 町で最も面積が広いのは、北海道の足寄町で、1408.04k㎡、2位は遠軽町、3位は別海町で、8位までが北海道でした。本州で最も面積の広い町は岩手県の岩泉町の9位で、992.36k㎡でした。最も狭い都道府県は香川県の1861.7k㎡ですので、足寄町の広さが解ります。なお岩泉町は、日本三大鍾乳洞の一つである龍泉洞で有名です。

306
答306 北海道福島町にある「伊能忠敬北海道測量開始記念公園」(青矢印)にありました。「大日本沿海輿地全図」を作成した際、蝦夷地測量は福島町吉岡から始まったとする記録が残っており、その功績を後世に伝えるため伊能忠敬没後200年の節目であった2018年に記念公園を建設したとのことで、公園内には銅像や功績を記す説明板(画像参照)などがあるとのことです。
305
答305 京都府京丹後市網野町磯にあります。地理院地図には記念碑の地図記号で表されていました。京丹後市のホームページでは、”日本標準時子午線、東経135度の最北の地に立つシンボルの塔。静神社に近い、日本海を望む景勝地にあり、日本標準時と世界標準時をデジタル表示しています。”との解説がありました。
304
答304 県庁所在地の方は、さいたま、たかまつ、うつのみやで、時間内に解けたのは、12名中4名でした。東京23区の方は、ぶんきょう、ちゅうおう、しんじゅくで、先に答えたのは、クイズ王で知られる伊沢でした。
答303 正解は長崎県で、高校生は正解していました。
302
答302 ”工場の地図記号が2013年に地図から消えた”とのことです。番組の中で国土地理院の説明があり、”大小様々な工場が増え、正確な把握が難しい、そのため維持管理が難しくなり、地図記号から外した”とのことでした。なお工場の地図記号はなくしても、大きな工場は名称で表現してあります。国土地理院のホームページの建物の地図記号を調べると、工場の地図記号はもちろん無くなっていました。
301
答301 ”ハザードマップと一緒に古い地図を活用!”でした。ハザードマップの活用法①として、家の周辺だけでなく、職場・学校の周辺や経路も確認する必要があるほか、小さな川や昔の池は埋め立てられたり暗渠となっているため、これらをも古い地図で確認する必要が説明されていました。そのため国土地理院のウェブサイトの活用も補足されていました。
300
答300 全部で98用語が掲載されていましたが、地図測量関係と思われる用語(カッコ内に掲載されている説明の概要を表示)は、①オリエンテーリング(地図を使って地点をめぐる競技)、②概念図(概略の地図)、③クロスベアリング(公会法)、④計曲線(50m毎の等高線)、⑤コンパス(方位磁石)、⑥三角点(測量に基準点)、⑦GNSS(衛星測位システム)、⑧GPS(アメリカの運用する衛星測位システム)、⑨磁北線(コンパスが示す北)、⑩主曲線(10m毎の等高線)、⑪準天頂衛星システム(日本の衛星測位システム)、⑫図郭線(地図の輪郭線)、⑬図幅(地図1枚)、⑭整置(地図を実際の地形に合わせる)、⑮測地系(地図の座標系)、⑯鳥瞰図(高所から見た形の地図)、⑰ディファレンシャルGPS(衛星データのほか基準基地からのデータで位置補正)、⑱等高線(標高を表す線)、⑲ハンディコンパス(手軽に携帯できるコンパス)、⑳標高点(標高が表示されている地点)、㉑標高差、㉒伏角(水平面と磁力線の方向とのなす角)、㉓ベースプレートコンパス(透明のプレートに磁針入りの回転式カプセルを取り付けたもの)、㉔偏角(真北と磁北との角)、㉕補助曲線(破線などで書かれた等高線)、㉖ロゲイニング(チェックポイントを多数設置したオリエンテーリング)、と26用語が掲載されていました。
299
答299 三角点、ジーピーエスと地形図の3用語でした。地形図は本書の解説があることが示されており、本書の56~57ページは「ガイドブックや地図にも慣れていこう」で、58~59ページは「地図から地形を読み取るには」のタイトルで、それぞれ説明がありました。
298
答298 ①トンネルは関門トンネルで、山口県と福岡県の県境でした。唯一県をまたいで歩ける海底トンネルです。②静岡県の浜松市です。浜松市の中の線は区界です。③リニア中央新幹線の路線図です。赤の実践は工事中のところで、破線は予定線です。④神奈川県の大和市と福島県の郡山市を重ねた大和郡山市は奈良県にあります。
297
答297 東経133度33分33秒、北緯33度33分33秒の地点である「地球33番地標示板」でした。地理院地図には記念碑の地図記号が表示されていました。なお経度・緯度の度,分,秒の同じ数字が12個も並ぶ地点は,全世界中で陸上にあるのは10ヶ所だけで、そのほとんどは砂漠や大平原の中にあり,容易に行くことができるのは,この「地球33番地」だけだそうです。
296
答296 伊能忠敬は55歳から全国を歩き地図を作り始め、73歳で亡くなるまで18年間地図作りを行っていました。その3年後弟子たちによって日本地図が完成しました。またアメリカ議会図書館で見つかった伊能大図は207枚にも上り、日本全国をカバーすることができるようになりました。
295
答295 答は地図でした。仁和寺にあったのは1305年作成の地図でした。説明はありませんでしたが、いわゆる行基図で、現存する行基図で最も古いものです。なお開いてなかったヒントは、モルワイデと伊能忠敬でした。
bottom of page